「誰一人取り残されない」を実装するデジタルプロダクト開発の現在 デジタル庁 統括官 楠 正憲
- 公開日:
タグ
「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化を」をミッションに掲げるデジタル庁において統括官を務める楠 正憲に、デジタル庁発足前から手掛けてきたさまざまなデジタルプロダクト開発の裏側と、利用者への思いを聞きました。
新型コロナ禍の3つのプロジェクトも担当
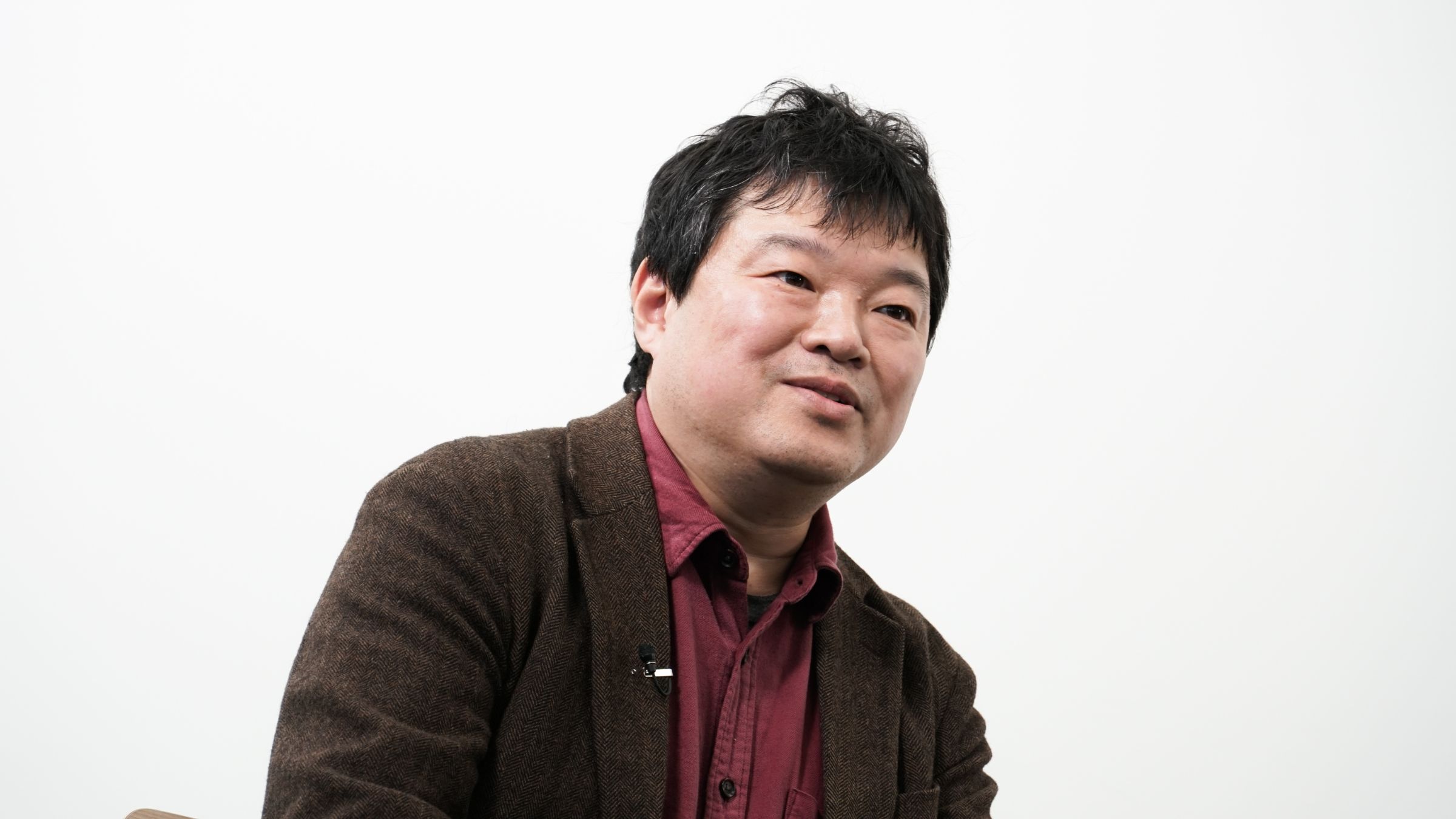
――これまで携わってきたプロジェクトについて教えてください
楠 デジタル庁が立ち上がる以前は、政府CIO補佐官(IT総合戦略室担当)を務めていました。その際には、マイナンバー制度の立ち上げに伴う情報提供ネットワークシステムや「マイナポータル」関連を担当していました。
新型コロナ禍以降、特別定額給付金のオンライン申請の構築や「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」にも携わりました。デジタル庁発足後は、「ワクチン接種記録システム(VRS)」や「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」なども担当しています。
――プロジェクトから学んだことがあれば教えてください
楠 マイナポータルの立ち上げに際して、設計中にどんどんブラウザの仕様がセキュリティ強化によって変わっていってしまい、プロジェクトに関わっていた私でさえログインに10分以上かかってしまうほど複雑になってしまいました。
そこから半年間ほどかけてつくり変えましたが、ある程度ベストを尽くした上での失敗は、変えるべきところと次にチャレンジをする時に避けるべきことが見えるため糧でしかないと感じました。それを生かして、ワクチン接種記録システムは短期間でしっかりとしたものをつくれたと思っています。
この1~2年間で大きな一歩を踏み出せている
――これまでの成果について教えてください
楠 行政機関は法律で定められた制度をもとに動いているので、この制度をきちんとデジタル化していくべきですね。世の中がデジタルに追いついていないというところを、どう解決していくかも大きなチャレンジだと思います。内製化が進み、徐々にプロダクトが出てくるという意味ではこの1~2年間で非常に大きい一歩を歩んでいると思います。
――デジタルプロダクト開発の現状の課題は?
楠 どのように民間ベンダーや他の自治体とのコラボレーションしていくのか、国の役割と市場で提供されるものとの関係を含め、まだ95%以上が整理できていない状態です。ものをつくれたらゴールではなくて、全体の底上げを産業としてどうすべきかを考えながら政策にどう落としていくかは、まだまだこれからだと思います。
しっかりチャレンジして、経験を積み、すごいと思ってもらえるような、世に問えるような、そういう世界も一緒につくらなきゃいけない。そのためには、調達の仕組みや組織のありよう、コラボレーションのやり方など、色々なことを変えていかなければと思っています。
――デジタルプロダクト開発を進めるために必要なマインドは?
楠 できるまで諦めなきゃいい、とりあえず「やってみます」と答えるしかないと思っています。誰かがやらなきゃいけないので、倒れるなら前に倒れた方が、後ろに倒れるより学ぶことがある。誰だって最初は初めてです。一度やると「できる気」がしてくるので、とりあえず挑戦してみたらいいと思います。
劇的に変わるAI技術の活用の現状

――昨今のAI技術の動向をどう捉えていますか?
楠 2022年から「Stabel Diffusion」というお絵描きAIや「ChatGPT」が出てきて、テキストでのやり取りだけではなく、画像を認識できるようになったりと、この1~2年間で状況が劇的に変わってきていると感じます。
――行政におけるAI技術の活用をどう捉えていますか?
楠 政府も含めてどう使っていくかという議論をしていますが、どこまで使えるかは実際に触らないと分からないですし、業務で使用する場合は、セキュリティの問題やデータ漏洩対策などさまざまな課題があります。便利だからどんどん使っていきましょう、というところまでは到達してないのが現状です。
社会でどう受け止めて、どういうルールをつくっていくか、今まさに議論をしている中で、みなさんが試せる環境を用意して、実際に肌感として理解した上で「まだ早いね」「ここから使おうか」というような地に足のついた議論ができるといいと思っています。
デジタルが押し付けられるようではいけない
――デジタルを多くの人が活用できるという視点で大切にしていることは?
楠 私は「ガジェット好き」なのでスマートフォンが手元にあればついつい触ってしまうし、新しい製品が出たら試してみようと思う方ですが、世の中、そういう人たちばかりではありません。
行政では手を差し伸べる必要がある方々に対してどうやって提供するかという視点が必要です。デジタルが押し付けられるようではいけないと考えています。
――デジタル活用における世代差はどう考えていますか?
楠 昔は、デジタルはお年寄りが苦手なイメージでしたが、それはもう違ってきています。例えば、今の職場の50~70代は私よりITができる人が多い印象で、むしろ今の子供たちの方がパソコンを使わなくなっているかもしれません。
そういう意味では、世代や地域の問題ではなく、その人の好き嫌いの時代になっていると言えると思います。みんながみんなITを使うというよりも、その人が心地良く生きていけるかに着目するべきと考えています。
(※所属・職名などは取材時のものです)
●デジタル庁ニュースでは、デジタル庁職員などのインタビューを掲載しています。以下のリンクをご覧ください。
●デジタル庁ニュースの最新記事は、以下のリンクからご覧ください。